浅日国三郎はこの地方の人々から村長(むらおさ)のように敬われていた。
この頃の国三郎は中肉中背で眉が太く、眼はキラリと鋭く、口は一文字に閉じていて、ちょっと近寄りがたいものを持っていた。
しかし、彼が微笑むとその笑顔は素晴らしく、誰からも親しまれる、不思議な魅力を持っていた。
子供の頃は頭がよくて、周りの人々から「天童」などと言われるほどだったと言う。
20代でいっぱしの実業家となった国三郎は自分のやりたいことは何でもやってきた。 |
 |
先ず、国三郎はこの地方の農家の人々が、農業の副業として作っていた生糸の原料の繭と、炭に目をつけた。
炭は灯油や、ガス、電力の普及が遅れていた当時の都会の人々にとっては、大切な燃料だった。繭と炭で財をなした国三郎は、30代でこの地方の町長になった。 |
当時の町長と言えば、現在のそれと違って、大変な力を持っていた。
「馬の用意が出来ました。」
馬引きの甚平が庭で待っている。
「おお、そうか。」 とうなずいた国三郎は妻のみなに向かって、
「今晩は川原湯温泉で宴会があるから、家には帰らない。」
「いってらっしゃい。」
みなと使用人数名が国三郎を送り出した。
国三郎はカーキ色の軍服と、同色の軍帽をキリリとかぶっていた。 |
 |
馬上の人となった国三郎の軍服にはいくつもの勲章が輝いていた。
美しい妻みなは、国三郎を見送ってからホッとため息をつき、淋しそうな、そして悲しそうな顔をした。
そこに居合わせた使用人は皆、その訳を知っていたが、誰もが黙って下を向いていた。
つづく 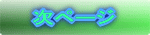 |
 《田舎暮らし&リゾート》
《田舎暮らし&リゾート》 《田舎暮らし&リゾート》
《田舎暮らし&リゾート》