森の精 作 唐松 緑 |
樹齢50年のからまつが半世紀をかけて作った細かい落ち葉のジュータンは、たいへん心地よいクッションになっている。
松井太郎がその上に横たわっている。
太郎が南木山(なぎさん)を歩く時は、くねくねした砂利道を嫌って松林の中を突っ切って歩いている。砂利道から松林に少し入ったところで、突然頭がくらくらとした。
高血圧症の太郎は落ち葉の上に倒れ込み仰向けに横たわった。目をつぶると落ち葉の匂いがする、風がからまつのこずえをなぜる音がする。自然と一体になった心地だ。
太郎は少し朦朧としてきた。
犬の激しい鳴き声で太郎は我にかえった。
「大丈夫ですか、犬が驚かせてすみません。」
秀雄が声をかけた。 |
 |
「いやー、落ち葉のクッションが気持ちよくて、つい寝てしまいました。」
「お休みのところを犬が騒がせて申し訳ありませんでした。」
「いえ、いえ。」 太郎は起き上がって、服についたからまつの落ち葉をパタパタとたたいた。
「私共の家はこの近くですが、よろしかったらコーヒーでも如何ですか。」 顔色の良くない太郎を見て秀 雄が言った。
「いやー、それは有難いですな。」
犬のジャーマンはうれしそうに尾を振って、三人の前を歩いている。
ログハウスのテラスは、丸太を組み合わせて造ってあり、白いテーブルと白い椅子が四脚おいてあり、テラスの隅には白い長椅子もおいてある。 |
「さっきはお倒れになったのでは、と少し驚きましたよ。」
「驚かせてしまってすみません。私は高血圧症でして、頭がくらくらとして横になったのですよ」
「ああ そうですか。でも、この山中で倒れたら心配ですね。」
秀雄は人ごとではない、という顔をした。
「私は携帯電話をいつも持っているのですよ。南木山(なぎさん)は山頂に通信会社のアンテナがありまして、携帯がどこでもよくつながるのですよ。本当に危ない時は携帯を押すことにしています。」
良子が香りの良いコーヒーを運んできた。
「いただきます、いやー 美味しいですね、元気になりましたよ。」
「松井さんは山菜を採るのがお上手とうかがっていますが、私にも教えていただけませんか。」 良子が云った。
「山菜取りが上手なのは、私ではなく桂木清さんですよ。」
「あの”森の精”とも 噂されているあの人ですか。」 |
 |
「私が山中を歩いていて迷ってしまった時に、あの人に会ったのです。初めて会った時は、はっとして本当に”森の精”が出てきたのではないかと思いましたよ。」
「一度お会いしてみたいですね。」
「あの人の涼やかで、清廉な美しさは何者にもたとえようがないですね。桂木さんと話をしていると、自分まできれいに洗われる思いがします。南木山を歩いていれば何時かお会いするでしょう。」
ピピ、ピピと秀雄の携帯が鳴った。電話を聞いている秀雄の表情がだんだんと変わっていった。
つづく 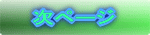 |
 《田舎暮らし&リゾート》
《田舎暮らし&リゾート》  《田舎暮らし&リゾート》
《田舎暮らし&リゾート》