サッと少し強い風が吹いて太郎の頬をなぜていった。
からまつの枝がザワザワと鳴っている。
太郎は高原の爽やかな空気を、オゾンと共に胸一杯に吸い込んだ。
ふと、大学のテニスコートでゆれる華子の長い黒髪が太郎の脳裏に浮かんだ。
黒髪をたぐるように遠い日の華子の姿が思い出される。
テニスコートでの華子の姿は眩しいほどに華麗で素晴らしかった。
華子はテニス好きの両親の影響で、小さい時からラケットをにぎっていた。
両親は華子には正しく、美しく、強いテニスプレイヤーになって欲しいという思いで |
 |
小さい時から専任のコーチを付けていた。
長じて華子のテニスが強く、華麗になったのは当然のことであった。 |
「華子さんのプレーはすばらしいね、君はテニスの基本をしっかり身に付けているよ」
「ありがとう、でも、太郎さんのテニスの強さにはとてもかなわないわ」
「僕のは我流で、ただひたすら練習と試合で鍛えたテニスだからなー」
「だから実戦に強いのよね、私などは試合になると対戦相手の迫力に参ってしまって負けてしまうのよね」
そういう華子を太郎は目を細めて眺めていた。テニスに限って言えば太郎も華子も、いわゆる世の中の「勝ち組み」に入っていた。
「あの頃は、青春の真っ盛りだったなあ」
太郎はからまつの枝の上に浮かんでいる |
 |
白い雲を眺めていた。
あの白い雲の眩しさは、青春の頃の華子の眩しさであった。
華子の可憐な美しさは北軽井沢の高原に咲くうすゆきそうのようであった。
太郎は、いつまでも、あきずにじっと白い雲を眺めていた。
つづく 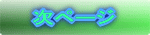 |
 《田舎暮らし&リゾート》
《田舎暮らし&リゾート》 《田舎暮らし&リゾート》
《田舎暮らし&リゾート》